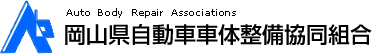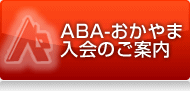- HOME
- 人材確保促進事業
- 職場環境改善マニュアル
- 良い人間関係をつくるためには
職場環境改善マニュアル 平成20年12月
良い人間関係をつくるためには
社員が退職する際の理由は様々ですが、家庭の事業がからんだ場合は別として、職場の人間関係がうまくいかないために辞めるというケースが最も多いようです。
上司との関係、同僚との関係、部下との関係など、職場には広範な人間関係がありますが、このメンタルな部分が最近では特に重視されているのです。確かに、人間関係がうまくいかない原因の一端が本人にある場合も少なくありません。それでも、職場の良好な人間関係をつくり出すための企業としての努力は、一日も怠ることは許されません。「鳥は枝を選んで巣をつくる」ように、社内の良好な人間関係こそ、従業員の定着を計る根幹の方策だといえるでしょう。
トップの言動
社長から役員に至るまで、経営陣の言動は常に従業員に注目されています。崇高な経営理念を説き、進軍ラッパを高らかに鳴り響かせ、アメとムチを巧みに使い分けようとも、彼らの言動が歪んでいたのではなんの意味もありません。
このような企業では、中間管理職はおのずと経営陣の悪いところを真似しますし、社員が面従腹背することも避けられません。
 従業員に嫌われるのは『公私混同』『わがままで自己中心的』『無理解な押しつけ』『優柔不断』『八方美人』などの言動で、個人的なスキャンダルも厳しい批判にさらされることになります。特に社員にとって耐えがたいのは、彼らの『言行不一致』です。このようなトップによる弊害は企業体質を致命的に悪化させ、人間関係を損ないます。従業員は企業に魅力を失い、徐々に従業員の定着率も低くなっていくのです。
従業員に嫌われるのは『公私混同』『わがままで自己中心的』『無理解な押しつけ』『優柔不断』『八方美人』などの言動で、個人的なスキャンダルも厳しい批判にさらされることになります。特に社員にとって耐えがたいのは、彼らの『言行不一致』です。このようなトップによる弊害は企業体質を致命的に悪化させ、人間関係を損ないます。従業員は企業に魅力を失い、徐々に従業員の定着率も低くなっていくのです。
中間管理職の資質
中間管理職の資質は、職場の雰囲気や部下の士気にどれほど影響を及ぼすか計り知れないものがあります。大勢の中間管理職がいる企業では、一部の中間管理職のあり方などは全体からみればとるに足らない問題のように思われますが、それはとんでもない誤りです。
たった一人の問題といえども見逃さず、妥協せず、キメ細かく手を入れて、中間管理職のレベルアップを図ることこそ、企業にとっての最大命題なのです。多くの中間管理職の中には、実務能力は備わっていても人間的資質に欠ける者がいないとは限らないからです。
資質の悪い中間管理職がいる職場には必ずといっていいほどトラブルが発生しますし、従業員の定着率も決まって劣悪なものです。
したがって、魅力ある職場をつくり出すためには、企業の中核ともいうべき中間管理職の質の向上を常に図ることが不可欠です。
中小企業人材確保推進事業